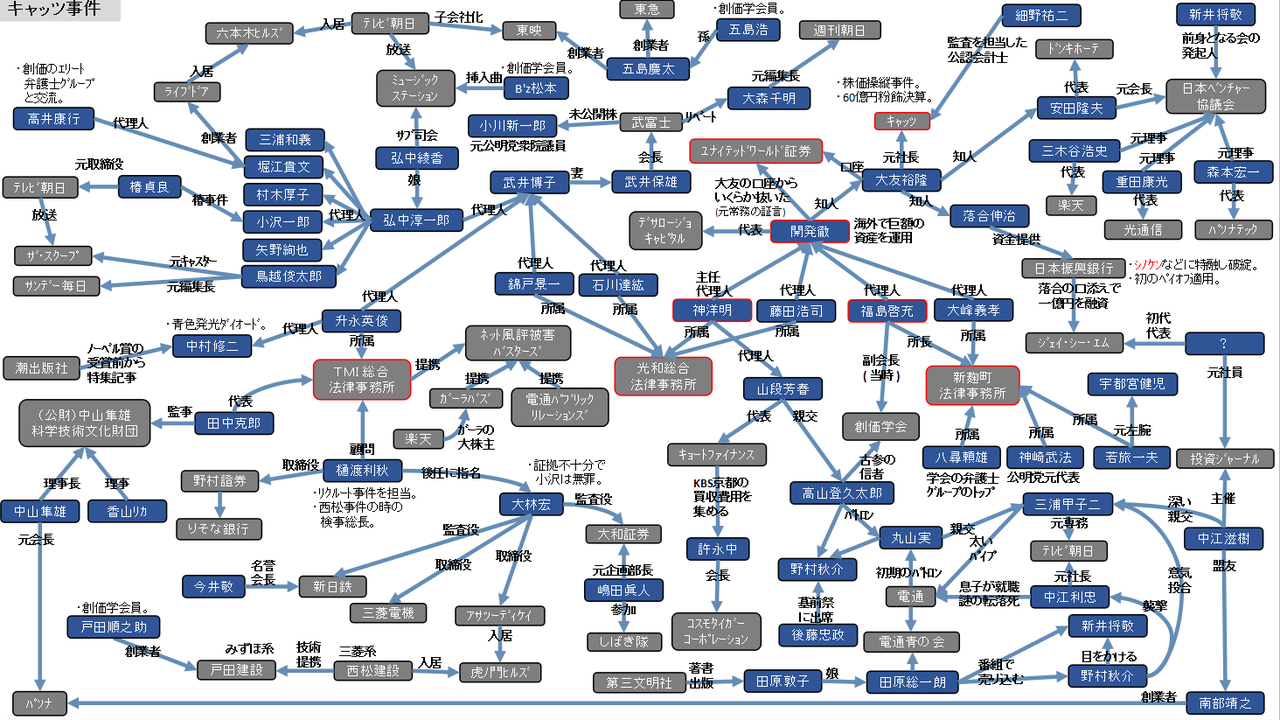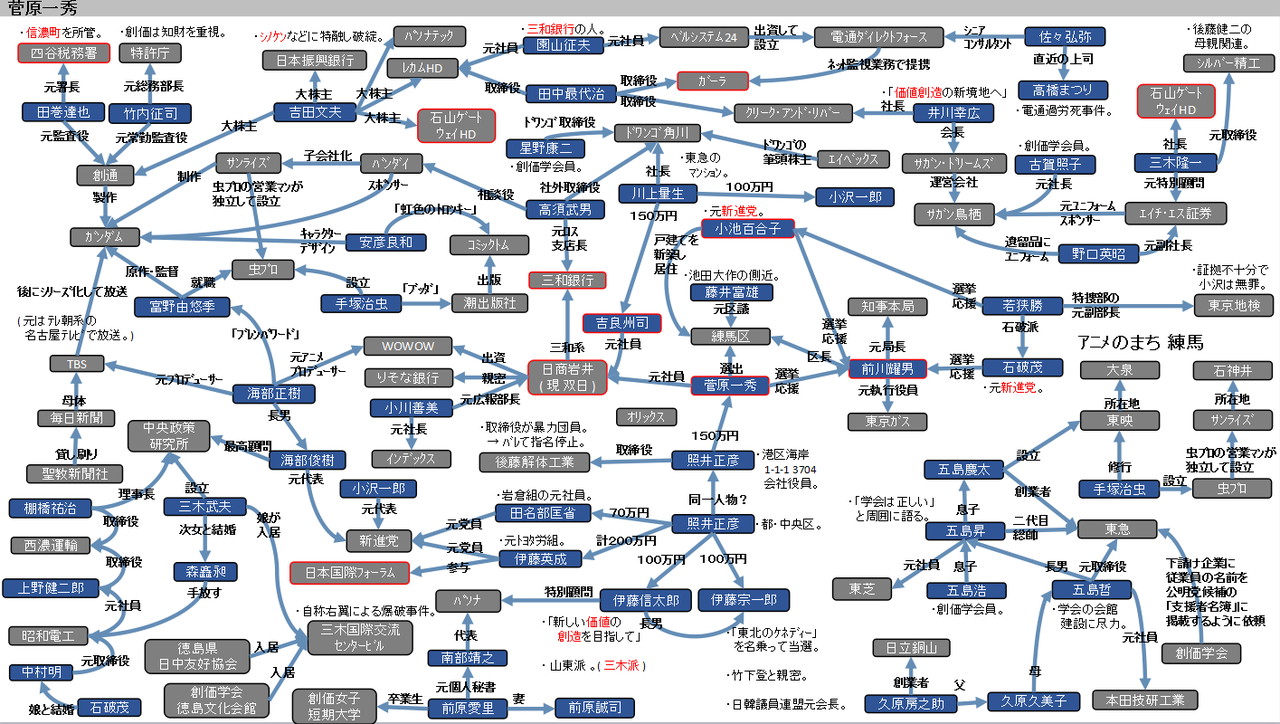同党の状況を見ているとそのとおりであるどころか、既に曲がり角に差し掛かっているように思われてならない。
■イロモノ議員の入党で政策的にブレる可能性大
安倍総理の施政方針演説への代表質問、記者会見や各種メディアでの発言、民進党との統一会派をめぐる発言を聞く限りにおいては、枝野代表は結党の理念を忘れず、衆院選で掲げた「国民との約束」からブレることなく真っ直ぐ、愚直に進んで行っていることに疑いを挟む余地はないだろう。
政策的には、「立憲主義に基づく民主政治」と「多様性を認め合い、困ったときに寄り添い、お互いさまに支え合う社会」の実現、国民の暮らしや働く現場の声を立脚点としたボトムアップの政治を目指し、共生社会づくり、税による再配分機能の強化、くらしの安心の確保等を進めるとしている。
前掲の拙稿でも指摘したとおり、結党時からのズレや変化が一部には見られるものの、枝野代表の発言と合わせて考えると、結党の理念から大きくブレたといったことはないと言えよう。
しかし、例えば、昨年末に民進党を離党して立憲民主党に入党した蓮舫参院議員の今国会での質問からは、党の基本政策から大幅にズレていくというかブレていく可能性が見て取れる。
具体的には、2月1日の参院予算委員会での本年度補正予算の審議の際、蓮舫参院議員の質問に通底していたのは、財政再建、プライマリーバランスの黒字化を達成せよ、歳出を削減せよ、そのために行革を進めよ、補正予算のせいで財政が悪化した、といったことだ。
立憲民主党の基本政策には、無駄の排除や財政健全化目標を定め持続可能な財政構造を確立することは記載されているが、それはとにかく歳出を削減しろということではないし、財政健全化目標もイコール、プライマリーバランスの黒字化というわけではない。
これでは、蓮舫参院議員の質問は立憲民主党の基本政策とは似て非なるものと言わざるをえない。かつて民主党政権下で行われた事業仕分けで担当大臣として名を馳せた、その過去の成功体験が忘れられないのだろうか。
しかし、それは民主党政権時代の話であり、社会経済の状況が変化している上に、立憲民主党は民主党ではないはずだ。これでは立憲民主党の基本政策を理解できていないのではないかとの疑問が湧いてくる。もしそうだとすれば、蓮舫参院議員が「声」が大きく目立つ分だけ、立憲民主党の基本政策とは異なる考え方が、さも立憲民主党の政策のように勝手に広まっていってしまう恐れがある。
■身勝手なキワモノ議員たち
一方で、まるでこうしたことに呼応するかのうように、立憲民主党の公認候補として当選したベテランのキワモノ議員たちが本性を現してきたようだ。
目立つための質問を半ば強制する
旧民主党系の悪い癖も徐々に姿を現し始めた
今や立憲民主党所属議員となった旧みんなの党系議員たち(以下、旧みんな系)と言えば、スキャンダル追及のような質問を忌避し、純粋に政策論の質疑を志向し、質問回数も多く、質問好きの議員が多い。
ところが、旧民主系が国対を仕切るようになると、そうはいかなくなってきているようだ。予算委員会の質疑はテレビ中継もされ、その審議は抜きん出て国民の注目が集まる、絶好の見せ場である。
注目を最大限惹きつけるために旧民主系が重要視するのは、相変わらず、目立つこと。そうなると、せっかく準備した政策論の質問は後回しにされ、場合によっては予算委員会ではなく他の委員会での質疑に回され(要はていのいい“ボツ”である)、スキャンダル追及や失言を引き出して上げ足を取るための質疑を優先するよう半ば強制されるといったことが起きているようだ。
旧維新の党と旧民主党が統一会派を組んだ頃から徐々にその傾向は見られたが、両党が合流して民進党が結党されて以降それが強まったようだ。それが民進党の分裂を経て、そうした旧民主系の悪癖というか悪習もリセットされ、枝野代表の下に集まった議員たちが新しい党の文化を創っていくのかと思っていたら、三つ子の魂なんとやらではないが、そう簡単にリセットされるようなものではなかったようだ。
http://diamond.jp/articles/-/160674
http://diamond.jp/articles/-/160674?page=2
http://diamond.jp/articles/-/160674?page=3
87あなたの1票は無駄になりました
2018/03/28(水) 17:32:29.38ID:m5n+nENK0