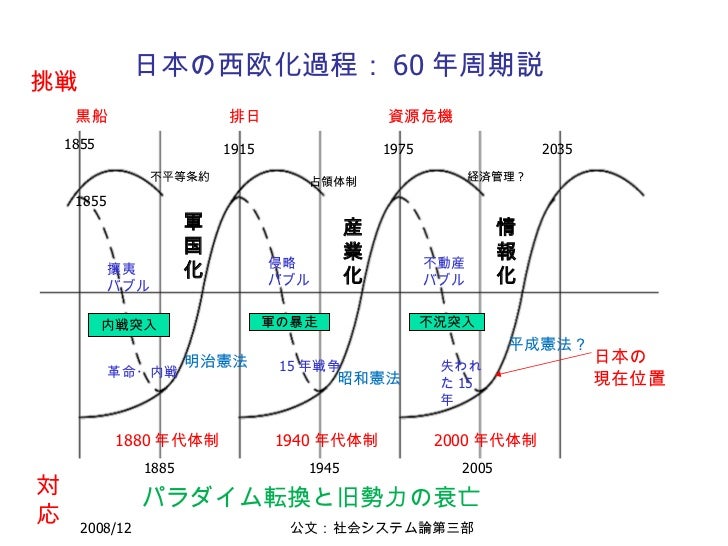https://jp.reuters.com/article/2018-views-hiroyuki-fujishiro-idJPKBN1EF0VS
2017年12月30日 / 02:54 / 12時間前更新
藤代裕之 法政大学社会学部准教授
[30日 東京] - 10月の衆院選でネット上に出回るニュースのファクトチェック(事実確認)プロジェクトに携わった藤代裕之・法政大学准教授は、5件の「フェイクニュース」を発見した。正体不明のニュースサイトや、ネット上の噂話などをまとめたサイトが主な発信源だが、中には一般向けニュースのポータルサイトに配信されて多くの人の目に触れたものもあった。
今後フェイクニュースが大きな影響力を持つ事態を予防するには、大きなニュースメディアやポータルサイトが責任を持って対策を講じる必要があると指摘する。また、広告主の役割も重要になると強調する。
同氏の見解は以下の通り。
<「疑わしい」記事総数は195本、自民党関連が最多>
10月22日に投開票が行われた衆院選の選挙期間中、ソーシャルネットワークやネットメディアに出回るニュースのファクトチェックを実行し、事実ではないことをさも事実であるかのように記事にした「フェイクニュース」を5件特定した。
読者は、5件と聞いて少ないと思われるだろうか。確かに、選挙の大勢に影響を与えるようなフェイクニュースは今回見つからなかった。だが、フェイクの芽というべき不確実な情報は大量に流れており、今後そうした情報が影響力を振るう事態を防ぐためには、ネットメディアなどを中心とした早急な対策が急がれる。
今回のファクトチェックは、任意団体「日本ジャーナリスト教育センター」(JCEJ)と、法政大社会学部の藤代研究室の合同プロジェクトとして行った。安倍晋三首相が解散を宣言した9月28日から投開票日翌日の10月23日までの期間、毎日1時間と時間を決め、学生9人が3人ずつのシフトを組んでツイッターを検索。政党名などを入力して、事実かどうか疑わしい情報を検索した。
その中からフェイクニュースの可能性があるものを、プロジェクトに参加した新聞やテレビなどの記者19人にメールで毎日送信。3人以上の記者が「事実ではない」と結論付けた時点でフェイクニュースと判定し、JCEJのサイトに随時掲載した。その件数が5件だった。なお、記者に送った「疑わしい」記事の総数は195件。1人以上の記者がフェイクと判断した記事の数は、5件よりずっと多かった。
5件の内訳は、立憲民主党の辻元清美議員に関するものが2件、安住淳元財務相に関するものが1件、立憲民主党に関するものが1件、そして外国人による選挙運動についてのものが1件だった。野党ばかりのようにみえるが、195件の不確実情報まで含めれば、自民党関連が一番多かった。ニュースバリューが高いものほど不確実な情報が出回る件数が多くなる傾向があると言える。
フェイクニュースや不確実情報は、正体不明のニュースサイトや、ネット上の様々な発言を集めた「まとめサイト」に掲載された記事を、匿名のツイッターユーザーがリツイートする形で、一定の範囲で拡散したものが多かった。情報の発信元や拡散の経路、拡散の範囲などについては今後分析を行うが、大まかな傾向として、以下のことが言える。
まず、特に野党関連の不確実情報をリツイートしていたアカウントの中には、「常習者」がいくつかあった。そのうちの1つのアカウントは、フォロワーが5万もいる。このようなフォロワー数万人規模の常習アカウントの間で相互にリツイートし合うことで、1つのフェイクニュースがある程度大きく広がるという構図が見てとれた。
動機はよく分からない。広告収入稼ぎではないように見受けられる。参加した学生からは、「拡散を狙うというより、仲間内で確認し合いたいのではないか」という感想も聞かれた。一方、正体不明のニュースサイトやまとめサイトは、バナー広告などを掲載しているものが多く、アクセスを稼いで広告収入を上げる狙いがあるとみられる。
問題のツイッターアカウントの中には、ヘイト的な内容も並行して流していたものが複数あった。不確実情報やフェイクニュースのトーンが排他的かつ攻撃的であることからも、ヘイトに親和性がある人たちではないかと推測している。また、欧米のフェイクニュースには外国政府の関与も報じられているが、今回の調査ではそれを疑わせるものはなかった。
(リンク先に続きあり)
2018/01/01(月) 07:12:24.60ID:wrlloxCt0
●紅白で安倍政権批判するNHK
どんだけ朝鮮人がいるんだNHK
紅白「NHKの敵」寸劇で政治活動
NHKの敵じゃなくてNHKそのものだろって思った。
民主主義を否定し不公平なフェイクニュースするNHKやテレビ朝日、TBSは日本国民の敵だぞ
NHKいわく「NHKの敵」、、
↓
「差別・忖たく・暴力・圧力」

フェイク、捏造、偏向、韓流ゴリ押しこそ国民の敵
どんだけ朝鮮人がいるんだNHK
紅白「NHKの敵」寸劇で政治活動
NHKの敵じゃなくてNHKそのものだろって思った。
民主主義を否定し不公平なフェイクニュースするNHKやテレビ朝日、TBSは日本国民の敵だぞ
NHKいわく「NHKの敵」、、
↓
「差別・忖たく・暴力・圧力」

フェイク、捏造、偏向、韓流ゴリ押しこそ国民の敵