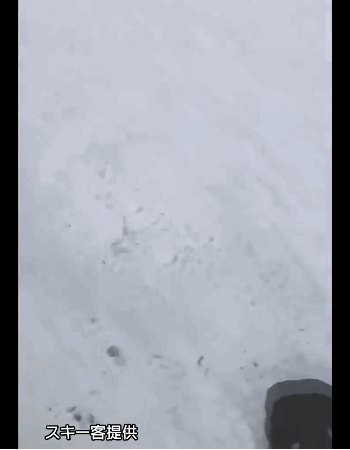https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180123/k10011299871000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_033
1月23日 21時03分
草津白根山の噴火について気象庁は、登山者などに噴火の事実をいち早く伝える「噴火速報」を発表しませんでした。想定していた火口とは別の場所で噴火が起きたことから監視カメラの映像がなく、すぐに噴火が起きたと判断できなかったと説明しています。
草津白根山では23日午前9時59分に噴火が発生しましたが、気象庁は噴火の事実をいち早く伝える「噴火速報」は発表せず、およそ1時間後の午前11時5分に「噴火が発生したもようだ」という情報を発表しました。
気象庁によりますと、噴火が発生した時刻には振幅の大きな火山性微動が観測されていましたが、このデータだけでは噴火と判断していませんでした。その後、地元の火山の専門家や草津町から「噴煙が上がっている」という情報が寄せられましたが、噴火を捉えた監視カメラの映像がなかったためすぐに確認できず、噴火から5分以内をめどに発表する「噴火速報」は出せなかったということです。
今回、噴火が起きたのは草津白根山の本白根山の鏡池付近でしたが、気象庁が噴火の可能性があると想定して観測態勢を整えていたのは、2キロほど北側にある白根山の湯釜火口でした。このため、監視に使っている3台のカメラは、いずれも湯釜火口に向けられていて、今回の噴火を捉えることはできなかったということです。
火山噴火予知連絡会の前の会長で東京大学の藤井敏嗣名誉教授は「噴火の確認に時間がかかったとしても、周囲にいる人やこれから山に登ろうとしている人に注意を呼びかけるために、『噴火したと見られる』と判断した段階で噴火速報を出すべきだった」と指摘しました。
気象庁は、今回、噴火が起きた場所の周辺を撮影できる監視カメラや地震計の設置など、観測態勢を強化することにしています。
11名無しさん@1周年
2018/01/24(水) 07:10:41.46ID:wIz0sCWF0